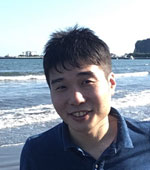当センターは以下のとおり3つの課題の解明、および3つの分野での開発を目指して、8つの分野における感染症研究に取り組んでいます。
解明すべき3課題
ウイルスはどのように増えるのか ウイルスはどのように病気を引き起こすのか ウイルスはどこにいるのか BSL- 4病原体を対象に、ウイルスの細胞への侵入から細胞内での複製、そして複製された子孫ウイルスの細胞外への放出までのメカニズムをウイルス因子と細胞因子の相互作用などから解き明かす。 BSL-4病原体がヒトに感染してどのように病気を引き起こすのかについて、細胞や実験動物を用いて明らかにする。 有効な感染症対策を講じるためには、感染症の発生をいち早く検知し迅速な対応をとることが極めて重要である。そのため発生地域、流行時期、環境要因、自然宿主及びヒトへの伝播を仲介する動物、伝播経路などを明らかにする。
開発を目指す3分野
検査・診断法 ワクチン 治療薬 BSL-4病原体による感染症は、早期の診断が感染拡大の抑止と患者の救命に極めて重要であるため、感染流行地や、検疫等の現場で活用できる精確・高感度かつ迅速な検査・診断法を開発する。 BSL-4病原体が引き起こす感染症に対するワクチンは、開発が遅れているので、次世代ワクチンを含め、感染あるいは発症の予防効果が高く副反応が弱いワクチンを開発するための研究を行う。 BSL-4病原体が引き起こす感染症に対する効果的な治療法はない。そのためウイルス増殖を抑制したり、症状を緩和する副作用の弱い治療薬の開発を行う。

| 新興ウイルス研究分野 | ウイルス生態研究分野 | ウイルス感染動態研究分野 | ウイルス免疫動態研究分野 |
| エボラウイルスなどの高病原性ウイルスやSFTSウイルスなどの新興ウイルスに関する基礎研究を行うとともに、これらのウイルスによる感染症の検査・診断法の開発や治療薬・ワクチンの開発を行っている。また、これらの感染症が発生するアフリカ、アジア、南米でウイルス感染症の発生状況の調査研究や野生動物における新規ウイルス探索研究も行っている。 | クリミア・コンゴ出血熱やダニ媒介性脳炎等の高病原性の節足動物媒介性ウイルスが引き起こす人獣共通感染症を中心に、ウイルスが自然界において節足動物等の媒介宿主の中で持続感染により維持され、宿主の壁を越えてヒト等の脊椎動物に感染して病原性を示していく「ウイルスの生態」を解明するための研究を行っている。 | 多様なイメージング技術を活用することで、ヒトに出血熱あるいは腫瘍といった重篤な疾患を引き起こすフィロウイルスおよびEpstein - Barrウイルスを対象に、各種ウイルスタンパク質が宿主細胞の膜動態や細胞骨格系を制御する分子機構に着目して感染および病原性発現機構の分子基盤を解明することを目的として研究を進めている。 | 公衆衛生上重要な問題となるウイルス感染症の流行防止対策のためには、ウイルス感染における免疫応答を理解するための宿主の研究が重要である。ウイルス感染における生体防御メカニズムを明らかにすることで、ウイルス感染症の流行防止対策の観点から、生体防御メカニズムを利用した治療法、ワクチンなどの予防方法に関する研究を進めている。 |
| ウイルス制御研究分野 | 感染分子病態研究分野 | 感染症糖鎖機能研究分野 | ウイルスー宿主相互作用研究分野 |
| 主に齧歯類が媒介し、ラッサ熱の原因となるラッサウイルスや南米出血熱の原因となる複数のウイルスに代表される「アレナウイルス」を対象に研究をしている。具体的には、アレナウイルスの細胞内・動物内での増殖機構を分子レベルで理解することで、アレナウイルスの病因や創薬標的を明らかとし、アレナウイルス感染症の制御を目指す。 | ウイルスが感染すると、生体内では免疫応答など様々な宿主反応が誘導される。また細胞に感染しないと自己複製できないウイルスは、複製するために多くの宿主機構を利用する。フィロウイルスやブニヤウイルスなどを対象に、ウイルス感染における宿主応答や、感染の分子機構を解析することで、発症メカニズムの解明を目指して研究を行っている。 | 糖鎖と糖鎖を認識するレクチンに注目して、ヒトに対して重篤な症状を引き起こすウイルス性感染症の研究を行っている。複数の動物種をまたいで生活環を維持するウイルスについて、宿主細胞の性状に起因するウイルス粒子上の糖鎖構造の差異が病態に与える影響を明らかにするとともに、糖鎖改変ウイルスを用いた新規予防薬の開発に取り組んでいる。 | 「ウイルス-宿主相互作用」をキーワードにウイルスのライフサイクルを制御している宿主因子を解析することにより、ウイルスの感染増殖複製機構の解明と新規抗ウイルス薬の開発を目指している。エボラウイルスなどの高病原性ウイルスを中心にAIDSの原因ウイルスであるHIV-1やレトロトランスポゾンLINE-1に関する研究も並行して行っている。 |
新興ウイルス研究分野
エボラウイルスやラッサウイルスなどの高病原性ウイルスを中心に、分子レベルでの増殖機構の解析、個体レベルでの病態解析、抗ウイルス薬・治療薬の開発、海外の流行地における生態系レベルでのウイルス調査などを行い、ウイルス感染症の制圧を目指しています。
所属する研究者
ホームページはこちらから↓
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/emerging/
ウイルス生態研究分野
私たちの研究室では、人に重篤な疾患を引き起こすウイルス性人獣共通感染症を対象に、主にベクター媒介性ウイルスについて、ウイルスの生態や伝播経路の解明、病態発症の分子メカニズムの解明、診断法、予防法、治療法の開発に関する研究を実施しています。
所属する研究者
ホームページはこちらから↓
https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/infection/
ウイルス感染動態研究分野
主に多様な顕微鏡技術を用いて、ヒトに重篤な疾患を引き起こすエボラウイルスおよびEpstein-Barrウイルスを対象として、ウイルス-宿主相互作用という観点から、感染機構および病原性発現機構の解明、ならびに新規診断、治療法の開発に取り組んでいます。
所属する研究者
ホームページはこちらから↓
(日本語)https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/nanbo/index.html
(英語)https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/nanbo/en/index.html
ウイルス免疫動態研究分野
ウイルス感染における免疫応答について、マウスを用いて理解し、予防や治療に役立てます。
所属する研究者
ホームページはこちらから↓
https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/kawasaki/index.html
ウイルス制御研究分野
我々はラッサウイルスや南米出血熱ウイルスなどのアレナウイルスを中心に高病原性ウイルスの制圧を目指し、ウイルスの細胞内複製機構・感染個体の病原発現機構の解析を軸として抗ウイルス戦略に繋がる研究を進めています。
所属する研究者
ホームページはこちらから↓
https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/urata/index.html
感染分子病態研究分野
フィロウイルスやブニヤウイルスなどによるウイルス感染症について、感染したウイルスが体内でどのように増殖し、なぜ重篤な病気を引き起こすのか、感染のメカニズムを解析していきたいと思います。
所属する研究者
ホームページはこちらから
https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/tsuda/index.html
感染症糖鎖機能研究分野
ヒトに対して重篤な症状を引き起こすウイルス感染症を対象として、糖鎖と糖鎖を認識するレクチンに注目して、病態発症のメカニズムを明らかにし、糖鎖に注目した新規診断法や治療法の開発に取り組みたいと思います。
所属する研究者
ウイルス-宿主相互作用研究分野
エボラウイルスやマールブルグウイルスなどフィロウイルスを中心にウイルスの感染増殖を制御する宿主因子や種の違いによるウイルスの増殖や病原性を解明し、フィロウイルス感染症の制圧を目指しています。
所属する研究者
ホームページはこちらから↓
https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/annex/ariumi/index.html
バイオリスク管理研究
BSL-4施設のバイオセーフティ、バイオセキュリティに関する安全管理を担当し、現在は施設設備の管理、運営計画の立案、実験室バイオセーフティプログラムの策定を行っています。また、病原体取り扱い実験に伴うリスク評価分析と新たなリスク低減手法の調査研究を行っています。